2024年09月15日
グロック26モデルガン ダミーカート仕様(タナカG17+KSC G26)

なんだか今年は自分でも凄く頭が冴えているなぁと感じる今日この頃です。
モノづくりの神様が舞い降りていらっしゃって、自分に力を与えてくださっているような、そんな不思議な1年でした。
先般投稿したS&W M3913モデルガンに続き、
再びモノづくりへの強い欲望と衝動が抑えられず、突貫工事でとあるモデルガンを作り上げてしまいました。
グロックといったらコレ!!というくらい大好きな、グロック26のモデルガンです。

グロックのモデルガンといえば、タナカがフルサイズのG17を出していて、現行はEvo2改と、アップグレードを続けていますが、
コンパクトの19やサブコンパクトの26は、いまだにつくられる気配がありません。
そんな状況に多くの諸先輩方がしびれを切らし、既に個人でカスタムされた事例が複数見られますが、
M3913で自信をつけた自分も後に続こうと、ついに行動に移した次第です。
(元々グロック26のモデルガンはずっと欲しいと思っていたのですが、まさか自分で作ることになるとは・・・笑)
諸先輩方の作品を拝見して参考にさせて頂いた結果、当方はKSCのG26のガワにタナカのG17のメカをぶち込む方法で進めることにしました。
タナカのメカはKSCのガワに比較的容易に移植できるという記事を目にしたので、まぁイケるやろと踏んでいました。
・・・正直舐めていました。
現実はそんなに甘くなく、結果としてかなりの大手術になってしまいました。

まずはスライド。タナカのスライドからブリーチブロックを取り外します。
ブリーチブロックはスライドと別パーツになっていて、接着剤で止めてあるだけでしたので、
ストライカーが収まっている穴にドライバーを突っ込んで、てこの原理で捻ると簡単に切り離すことができました。


当然、タナカとKSCではスライド内部の形状が異なりますので、ブリーチブロックが収まるよう、KSCのスライド内部をリューターでゴリゴリ削ります。


さらに、KSCのスライドはエキストラクターがモールドになっているので、タナカのエキストラクターが入るよう、赤線内部を削ります。


削ってははめてまた削っての微調整を繰り返し、何とか収めることができました。
ちなみにエキストラクターが収まる面の反対側に、アクリル板から切り出したスペーサーを入れています。
スライドだけでもかなりの切削加工が必要で大変でしたが、本当の地獄はここから。
最も苦労したのは、実はフレーム側でした。

トリガーグループハウジングが収まるフレーム後方(ガスブロで言うとインナーハンマーが収まる部分)は、
なんとタナカとKSCで非常に構造寸法が似ており、赤丸部分のねじ穴とその他少しの加工ですんなりメカが収まるという奇跡で、
コレはイケるんじゃないか??とテンションが爆上がりしました。

・・・と安堵したのもつかの間。
問題はトリガーが収まるロッキングブロックハウジング。
なんとトリガーピンとロッキングスライド(スライドを止めていて分解時に押し下げるレバー)の位置関係が最大で3mm近くズレており、
そのままでは全く使い物になりません。

見た目が悪くなるので外側の樹脂フレームを削るワケにはいかず、亜鉛合金製のロッキングブロックハウジングを削って、穴位置を合わせる必要がありました。トリガーピンの穴を基軸として(ここは動かせない)、ロッキングスライドの位置を手前にずらしました。
この3mm、数字だけでみると大した距離ではないのですが、リューターで金属を切削加工するには非常に大きな数字で、最も時間と気力を使う作業になりました。
それだけではなく、ロッキングブロックハウジングが元々フルサイズの17用の長さになっているので、そのままではフルストロークでスライドが後退できず装填排莢ができないため、結局赤線部分を大きく削る必要がありました。

半日格闘して、何とか狙った寸法にすることができました・・・(しかも加工しやすくするため二分割しちゃいました)
これでとりあえず、無事に最大の難関を突破した次第です。

タナカのフレームに対してKSCは内側がやや薄く、そのままではマガジンが入らないので、赤枠部分をやすりで削り落としました。
あと、撮り損ねたのですが、ロッキングスライドスプリングを差し込む孔をフレームに開けたり、
シリアルナンバープレートを貼ったりして、フレームは完成です。

バレルはタナカのを切って再接着したのですが、寸法を間違えて短く切りすぎてしまったので、
先っちょをパテ盛りして長さを稼ぎました。
最初は肉薄にし過ぎて40口径みたいになってしまいましたので、後に修正しました。


マガジンはタナカG17用をぶった切って、26用のショートサイズにしました。
とりあえず試作用に切っただけですので、残弾孔を10発に直したり(パテ埋め)、上部の9mm刻印&下部のGLOCK刻印を彫るのは追々やりたいと思います。

塗料はインディのメタルパーカーを選択。
やや青みがあり、手軽に金属感を出せる素晴らしいスプレー塗料です。
塗った直後は艶消しですが、コンパウンドで磨くと光沢が出て、より一層金属感が出せます。
こんな感じで思いつくことわずか2週間で、ひとまずカタチにはなりました。







ガワはKSCなのに、中身はモデルガンという、他にない強烈な個性に優越感を覚え、所有欲を満たしてくれます。
ホールドオープン時に見えるダミーカートがたまりません。
エキストラクターが第二世代の形状のままだったり、
KSCの仕様でフレームのグロック刻印がなかったり、
チャンバーとスライドの高さがズレていたりと、
まだ手直ししたい部分はあるものの、総合的には満足する出来になりました。
一応メカはタナカなので、ガシャコンして装填排莢は可能です。
ただ、リコイルスプリングがG26のままで弱いので、引いて離しての装填ができません。
ここはまた適当な強さのスプリングを探し出して交換したいところ。
次はいつになるか分かりませんが、この調子でまた何かモデルガンを作れたらと思います。
今回はここまで。ではまた。

2024年07月07日
S&W M3913 モデルガン(マルシンM39ベースカスタム)

この趣味を長く続けていると、欲しい銃がトイガンとしてモデルアップされていないという悩みに直面することがあります。
マニアックなモデルはファンから根強い人気があるものの、
一般的には中小企業に相当するトイガンメーカー各社としては、この手のマイナーモデルをラインナップに加えることは、
商業的に成功するか、ある種の博打であり、かなりの高いハードルになるのではないかと思います。
僕にとっては、日本警察が一部で採用している、S&W M3913がまさにそんな銃でした。
通常の警察官はご存じの通り5連発の回転式が主流ですが、
銃器犯罪への対処が想定されている一部の部署で使用されている、米国S&W M39シリーズ直系の第三世代コンパクトオートです。
元々日本警察拳銃の大ファンで、その魅力にどっぷりはまっていたので、M3913は憧れの的だったのですが、
当然トイガンメーカーからはモデルアップされておらず、一部の業者(旭工房、マッドポリス等)がカスタムしたものがヤフオクにごくたまに出回る程度でした。
どうしてもM3913が欲しい・・・そんな時、久しぶりに僕にモノづくりの神様が降りてきて、呟かれました。
『ないものは、つくってしまえ、モデルガン』
今や発信活動の拠点をTwitter(X)に移してしまっており、久しぶりの投稿となり恐縮ですが、
今回は僕がマルシンのM39をベースに気合と情熱だけで作り上げてしまった、
S&W M3913モデルガンの製作過程をご報告したいと思います。

今回、2機の試作機を製作。
左が初号機、右が弐号機となります。
元々は初号機のみ製作するつもりでしたが、
色々納得がいかず、もう1機作ってしまった次第です(笑)。

まずベース機はマルシンのM39にしました。
MGCのも中古市場で割と数が出回っているのですが、
既にメーカーが存在しておらず今後の部品入手性への不安があり、
マルシンのほうが良さそうと判断した次第です。

製作前に比較と現状把握をしたのですが、実は一筋縄にはいかないことが判明。
単純にスライド、バレル、フレームをぶった切って塗装するだけではなく、
そもそも世代差が伴う大きな違いが両者にありました。
・バレルブッシングの廃止によるスライド前端形状の違い
・バレル形状の違い
・アイアンサイトの違い
・フレーム形状の違い(グリップの角度の違い含む)
・グリップ固定方法の違い
・サイドプレート形状の違い(第三世代はスライドストップリリースレバーを押さえる機能も兼ねる)
等々・・・
これらの問題を一つ一つ考えながら、解決していきました。

まずはスライドからぶった切り・・・

ブッシングレス化に伴い、スライドに細工を施します。とりあえず適当な径の塩ビパイプを切り出しやすりがけしてサイズ調整。

それをスライドにはめ込み接着し、バレルスペーサにしました。

ブッシングレス化によりリコイルスプリングが抜けてしまうので、固定用にサイズ違いのアルミパイプ2種を切り出し・・・

スライドに埋め込み接着。これでリコイルスプリングが固定されるようになりました。

バレルもこんな感じでぶった切り・・・

先っちょだけ接着し、やすりがけして独特なくびれ形状を作りました。

スライドとバレルを組むとこんな感じに。

リコイルスプリングガイド等をぶった切り。
リコイルスプリングは最初純正を切って入れてみたものの、線径が太く、バネ自体も硬く短縮には向かなかったため、
後により線径が細く柔らかいものを業者に発注しました。

アイアンサイトは、他モデルのものを加工して流用。
初号機はマルイM45A1用のサードパーティ製(3Dプリンター品)を加工しましたが、その業者の対応がイマイチだったので弐号機では採用せず、
フロントはマルイP226用を、リアはマルイV10用を加工しました。

エキストラクターについては、初号機はベースのマルシンM39そのままの機構にしたので、
マルシンのエキストラクターにアルミ板を貼っただけにしたのですが、これではリアリティに欠けるため、
弐号機ではマルシンのBHPミリタリー用を加工して取り付けました。
ちなみに、マルシンM39はブリーチブロックが前後に動いてしまうため、
エキストラクターのライブ化にあたりエキストラクターピンがブリーチブロックの固定ピンを兼ねる構造にしました。
これでブリーチブロックは後退位置で固定されます。
(ブリーチブロックを後退位置にしないと、スライドを目いっぱい後退させても弾が装填できなくなります。
M3913化にあたり、機構構造面のアドバイスを、M3913化カスタムの第一人者である港3号さん(Twitter(X)では『リオ』さんとして活動)より頂きました。有難うございました!)

マルシンM39は本来U.S.A.刻印の箇所が『J.S.A.』になっているので、
『U』になるように彫り直しました。

さて、難しかったのがフレーム。
まず末端をぶった切るまでは良かったのですが・・・

M39とM3913ではグリップ前部の角度が違うため、グリップパネル前端の傾斜角に合わせて、前端をひたすら削って角度修正しました。

グリップパネルについては、初号機はホーグ製、弐号機はS&W純正品を採用したのですが、
固定方法が異なるので、フレームはまったくの別物になりました。

まず初号機は当時ホーグ製のグリップしか入手できず、入手した個体は本来付属しているねじや固定ブロックが欠品していたので、
フレーム後端にパテを盛り、穴を開け、六角ねじで固定する方式を採用しました。

一方弐号機の時はS&W純正のグリップが手に入ったので、それに合わせてアルミ板を切り出して穴をあけて固定金具とし、
そこにグリップピンを通して固定する方式にしました。

ちなみに純正グリップの内側には赤枠の突起があり、そのままではうまくフレームにはまりません。

そこでフレーム内側の緑枠部分を削って、グリップ赤枠部とうまく噛み合うような構造に修正。

修正後はこんな感じに綺麗にはまってくれました。

ちなみに、弐号機で入手した純正グリップですが、実はM3913用ではなく、45口径のM4516用。
グリップ前端がM3913用よりやや厚く、マガジンキャッチ周辺の突起がやや出っ張っているのが特徴です。
M3913に使うには、前端部を加工してやる必要があります(このあたりの情報も港3号=リオさんからご教示頂きました)。

前端加工後のグリップ。
ちなみに、マガジンキャッチの反対側もM3913っぽく形状変更しました。

トリガーガードもM39とM3913では形状が異なり、
雰囲気を出すために何度もパテを盛っては削ってを繰り返し、
何とかそれっぽく仕上げました。

ちなみにトリガーガードとグリップ前端のチェッカリングは、
当初筋目やすりで彫ることも考えたのですが、値段が高く技量的にも自信がなかったので、
WAのショーティ40から型取りして、プラリペアでパーツを作って移植しました。

移植・接着したら余分な部分をカットし、フレームとの継ぎ目にパテを盛って目立たなくします。

マガジンキャッチスプリングの位置がM39とM3913で異なるので、オリジナル位置をパテ埋めし、
新たに穴を設けました。

僕にとって最大の難関が、刻印の手彫り。
弐号機にはAで始まる警察管理番号も入れました。
ベースになるフォントをエクセルで作って印刷して貼り付け、
上からミシン針でひたすらツンツンしました。
ちなみに針はミシン用のものを削って鋭利にしたうえで、ピンバイスに取り付けたものを使いました。
(この技法は、我らトイガンカスタム界の巨匠、オラガバニストのあじゃさんにご指導頂きました。有難うございました!)

ツンツンし終えたら紙を剥がしてひたすらホリホリ。
虫眼鏡を使いながらの作業です。
幸い僕はまだ老眼ではないのですが、それでもつらい・・・へたっぴですが3時間かけてなんとか彫り上げました。

もちろん金属部品にも手を加えます。
ハンマーはちゃんとデホーンドタイプに加工。

ハンマーピンを兼ねるサイドプレートはM39と構造が異なるので、
ハンマーピンは4×20mmの平行ピンを手配、
サイドプレート部分については、初号機はWAのショーティ40のものを流用、
弐号機はアルミ板から切り出して加工し、平行ピンに接着しました。

マガジンも短縮加工。
末端に切り込みを入れ、横に曲げます。

ある程度曲げて余分なところをぶった切ったら、適当な木片をはさんでバイスに固定し、
耳部分をハンマーで叩いてまっすぐに曲げてやりました(この技法もあじゃさんにご指導頂きました)。

マガジンバンパーについては、マガジンの耳が通る部分だけアクリル板を積層にし、以下はパテを盛って成形しました。


弐号機の塗装前状態。
塗装前にひたすらやすりがけも行いました。


塗装はキャロムショットのスプレー缶を使用。
スライドとバレルはステンレスシルバー、フレームと金属部品はチタニウムシルバーで塗装しました。
スライドとフレームを塗り分けることで、S&W第三世代オート特有の雰囲気を再現しました。

日本警察仕様の特徴であるランヤードリングについては、マルイのM9用を加工して取り付けました。
こんな感じで試行錯誤を重ねた結果、何とか完成しました。
製作期間は2丁で計3カ月という感じです。






初号機である程度工法を確立し、弐号機で発展改良したという感じです。
急いで作ったので仕上げの粗さや雑さが目立ってしまったのが反省点ですが、総合的には満足です。
ちなみに日本警察に採用されているモデルは後期型ですが、
刻印がどう頑張ってもレーザー刻印じゃないと彫れないものでしたので、
あえて、『1991年に前期型がごく少数試験導入された』という架空設定で、前期型にしました。
4月にエイプリルフールネタとして思いついたことがきっかけで、まさかここまで形にできるとは思いませんでした。
今回の企画に際しご支援・ご指導頂きました皆様には、この場を借りて感謝御礼申し上げます。
今回はここまで。ではまた。

SPECIAL THANKS:
港3号(=リオ)様
オラガバニスト あじゃ様
2023年03月05日
【番外編】コルト キングコブラ 2.5インチ(東京マルイ コルトパイソンカスタム)

中古市場では、時としてとんでもない掘り出し物に巡り合うことがあります。
トイガンでも、既に生産終了した絶版品や、長らく探し求めていた銘品、珍品と運命的邂逅をすることがあるので、ガンショップ通いがやめられません。
月に一度は必ず訪れる、大阪日本橋の中古ガンショップのショーケースに、今回のお題は眠っていました。
思わず二度見して笑ってしまうくらいの珍品。
そう、本来ガスガンとしては市場に存在し得ない、コルト キングコブラでした。
今回は番外編として、東京マルイのガスパイソンをベースにカスタマイズされた、コルト キングコブラについて語ろうと思います。

その前に簡単に実銃の話を。
コルト キングコブラは、1980年台後半から90年台にアメリカの老舗コルト社から発売されていた回転式拳銃。
パイソンやダイヤモンドバック、アナコンダ等、蛇の名を冠するモデルのひとつです。
先行するトルーパー MK.Vをベースに、.357マグナム弾の発射を前提とした耐久性重視の改良が加えられ、さらにフレームやバレル等主要部品に錆に強いステンレスが採用されました。
本体色は基本的にステンレスむき出しのシルバーですが、ブルーイングが施された黒いモデルもあるもよう。
1998年頃を最後に生産終了となっていましたが、2019年にリバイバル。各部に設計変更が加えられながらも、現在も生産が続いているようです。
※ソース:https://www.colt.com/series/KING_COBRA_SERIES
キングコブラの2.5インチと言えば、個人的には柴田恭兵演じる『あぶない刑事』のユージ(大下勇次)を連想します。
『リターンズ』と『フォーエバー』でユージのメインウェポンとして活躍しました。
(実はこれが買った一番の理由だったりする・・・)
さて、キングコブラのトイガンですが、冒頭に少し触れた通り、BB弾が発射可能なガスガンとしては、本来市場に存在しません。
唯一トイガンとしてラインナップされているのは、KSCのモデルガンのみとなります。
今回のモデルは、恐らくはキングコブラが大好きで工作技術を持った方が東京マルイのガスパイソン2.5インチをベースに、
KSCのキングコブラ2.5インチのアウターバレルとニコイチで制作したカスタム品と推測しています。
それでは細部を見ていきましょう。


全体像。
パイソンを見慣れている方からすれば、すごい違和感があるでしょう。
ただ、キングコブラのバレルとパイソンのフレームが、びっくりするくらいマッチしています。
厳密にいえばキングコブラとパイソンはフレームの大きさが異なる(パイソン:Iフレーム、キングコブラ:Vフレーム。パイソンのほうが小さい)のですが、
そんなことが気にならないくらい、見事な仕上がりだと思います。

バレルまわり。
こちらはKSCのキングコブラ2.5インチのものを移植した模様。
中をくりぬきインサートなども除去し、できた空洞にさらに別の銃のアウターバレルをねじ込み接着し、
パイソンのインナーバレルが通るように加工されているように見えます。
なんというか、これはプロの仕事ではないかと。その出来栄えに、思わず脱帽です。

以降は東京マルイのガスパイソンに準拠する内容ですので簡単に。
トリガーはシングルアクション・ダブルアクションともに軽い引き心地。
トリガー上部のねじ位置やフレームラグの形状がパイソン準拠で、本物のキングコブラとは異なるのはご愛敬ということで・・・

グリップはパックマイヤー風で、ラバーコーティングがされています。
経年劣化でベタ付かないか心配ですが、その前に本家のパックマイヤーのグリップを入手して、内側をくり抜いて、装着してみたいところ。

ちなみにグリップを外すと、中には本来メインスプリングが入っている場所にガスタンクが入っています。

ハンマーまわり。
ハンマーの直後にはガスガン独自のマニュアルセーフティが備わっており、前に押すとセーフティオン。
ただこれが勝手にかかってしまったりと非常に邪魔なので、早々に取り外しました。

ハンマーは比較的軽い力で起こせます。
ガスリボルバーとしては一般的な、不正改造防止の板が見えます。

バレルの反対側面の刻印も、KSCのキングコブラと同様。
フロントサイトの赤いマーキングが、なぜか素人が塗ったような仕上げになっていて、ニコイチ加工の技術力とのギャップにびっくり。
ここはボーディさんのボディガードのように改善の余地あるかも。

フレームのASGKとMADE IN JAPANは、せっかくだから消して欲しかったところ。
シリンダーは時計回りでスミス&ウェッソンは逆回転。
スミス&ウェッソンに慣れているとちょっぴり戸惑います。
非常に軽くおもちゃっぽさがあるものの、よく回ります。
ちなみにシリンダーは左側面後部のラッチを後ろに引っ張るとロックが外れてスイングアウトできます。

スイングアウトしたシリンダー前部。
レンコンの孔口径がBB弾に準拠した6mmと小口径なのが残念ポイント。
実射性能を重視した結果ですので仕方ないですね。

本来のガスパイソンはシリンダー内に各4発のマガジンが内蔵されており、これにより24連射が可能となっているのですが、
このモデルはカート式にカスタマイズされており、見事な筒抜けっぷりです。
東京マルイのガスリボルバーの最大のメリットを封じるカスタムですが、
浪漫のほうが大事なのよ。

カートはキャロムショットのものが付属していました。
マルシンのXカートと同様、先っちょにBB弾を一発ずつ詰めます。
(右上は比較用の.38スペシャルのダミーカート)

キャロムショットのカートを装填するとこんな感じ。
ダミーカートと違い、カート底部がやけに膨らんでいますが、その理由は後述します。

シリンダーが筒抜けになったことで、ダミーカートも装填できるようになりました。
ただ、残念ながらダミーカート装填時、およびカート未装填時は、仕様によりシリンダーが回転せず&ハンマーコックできず空撃ちできません。

その理由が、東京マルイ製ガスリボルバーの特徴にして欠点でもある、可動式ガス放出孔。

この放出孔は、ハンマーコック時と発射時に写真のように前に突出してシリンダー部に張り付くことでガスルートとシリンダーの気密性を確保し、
ガスの漏れやロスをなくすという独自の機構を有しているのですが、発射後トリガーとの連動やスプリング等により後退するというギミックはなく、マガジン(このモデルではキャロムのカート底部の膨らみ)に押し戻されることで後退する機構をとっています。
従って、マガジンもしくはカートが入っていない状態では、放出孔が出っ張った状態のままで後退しないため、シリンダーと干渉して回らなくなってしまうというわけです。
(この状態になったら、絶対に無理にスイングアウトしないでください。最悪の場合放出孔が破損します!)

ちなみにこの個体は買って即空撃ちしていた段階で、ハンマーやトリガーの感触にどうにも引っ掛かりを感じたので、
分解注油することにしました。
まずはシリンダーを外します。フレーム右側面、トリガー上部のねじを外せば、シリンダーを取り外しできます。

シリンダーを外したら、フレーム左側面の3つのねじを外してサイドプレートを外します。
内部は実銃とは似つかない複雑なメカをしている印象です。
簡単にほこりを取っ払ってからシリコンオイルを注油して組みなおした結果、ハンマーもトリガーも、引っ掛かりなくスムーズになりました。

とりあえず手持ちの、イタリアVega Holster社のIB339に挿してみた図。
IB339はオートマチック用なので当然リボルバーには合いませんが、インサイドパンツホルスターなので実用上は問題なさそう。
IB339は『007 カジノ・ロワイヤル』でダニエル・クレイグ演じるジェームズ・ボンドが使用していたことで有名。
ボンドのホルスターにユージのキングコブラという、とってもセクシーな組み合わせ。
さて、実射性能はというと・・・正直カート式リボルバーという感じの結果。
もともとのオリジナルは、マック堺さんのレビュー動画の通りなかなかの命中精度をもっていたものの、
この個体はカスタムの影響か、もしくはカート式にしたせいか、はたまた冬場の外気温(11℃)が悪さをしていたのか・・・
どうにも安定しませんでした。

0.25gを8mから6発、10セット程繰り返してようやく出たベスト結果がコレ。
一発は大きく外してしまいました。
左右のブレは少ないものの、ガス圧が安定しないのか、ドロップ気味の弾道かと思えば急にまっすぐ飛んだりと、とても実戦投入できそうにありませんでした。
初速も今手元に弾速計がないので計測できていないものの、40m/sもないくらい遅めに感じました。
総括として、実射性能はまだ改善の余地はあるものの、キングコブラのガスガンに巡り会えただけでもう十分というのが正直な感想です。
この作品を作り上げた方の発想と技術力、そしてキングコブラへの情熱と愛をひしひしと感じました。
どういう経緯で制作され、手放されてしまったのか知る由もありませんが、新たな出会いに感謝し、これからも大切にしたいと思います。
尚、ベースの東京マルイ製ガスパイソンも今や絶版品で、故障時パーツの確保が課題となりそうです。
(幸いまだ中古市場には転がっているようですが)
今回はここまで。次回もお楽しみに。
追伸:
気になって調べてみたところ、どうやら大阪のとあるショップが限定で制作したカスタムモデルのようでした。やっぱりプロの犯行で納得!
※ソース:https://www.airgun.jp/html/products/detail.php?product_id=12359

2020年11月01日
東京マルイ グロック17 Gen2(Gen3ベースカスタム)
東京マルイのグロックとは、非常に長い付き合いになります。
これまでに26、17 Gen3、18C、19を使ってきましたが、特に17 Gen3は長らく愛用してきました。
今でこそ最新の19や17 Gen4には性能でもリアリティでも敵いませんが、発売当時はあの東京マルイからやっとフルサイズのグロックが出た!!と興奮したものです。
昔々、お金がなかった学生時代、ジャンク品の17 Gen3を安く仕入れてきて、コツコツ部品を買って修理し、カスタムしたのはいい思い出です。
構造から市場に出回っているサードパーティ製のカスタムパーツまで知り尽くしていて、もはやずっと一緒にバディを組んで戦ってきた戦友というか、長年連れ添った女房というか、そんな立ち位置とでもいうべきでしょうか?
そんな愛銃グロック17 Gen3ですが、自分のイメージの中でほぼ完成形に近い形にまで仕上げ、現在に至ります。
フレームがGen2になったりと、もはや原形をとどめてはいませんが、今回はこの場で少しお時間を頂いて、そのカスタムのレシピを公開したいと思います。
【基本コンセプト】
東京マルイのグロック17 Gen3をベースに、個人的に大好きなGen2の実銃どノーマル品に可能な限り近づけるカスタムを行っております。
尚、内部パーツに作動性向上を重視した部品選定を行い、性能面でも近代化改修を図っています。
『ガワは旧式、性能は最新』もしくは『羊の皮を被った狼』といったイメージです。
Gen2って、1990年代に流行ったアクション映画に数多く登場しているんです。
それを見て育った自分にとっては、Gen3以降のモデルもいいけどGen2のほうが、クラッシック感があって好みなんですよね。
(あと、個人的にはダストカバーのレールやグリップのフィンガーチャンネルが嫌い)
使っているカスタムパーツについては、以下に列挙していきます。
【スライド】
①GUARDER スチールナイトフロントサイト(ホワイト)
ローライトコンディションでも狙いはつけれるように、蓄光タイプにしました。
ただし、あくまで実銃どノーマルを意識して、純正品と同じ形状にしています。
②GUARDER ライトウェイトアルミブリーチ
作動性向上の肝となるパーツ。亜鉛合金製のノーマル51gに対し、なんと20gの軽さ。
これによってリコイルは激減しますが、スライドはシャキシャキと寒くても比較的素早く動くようになります。
旧型エンジンではどれだけ頑張っても、リコイルにおいては最新のグロック19や17Gen4には敵いません。
であればそれを逆手に取り、むしろ限りなくリコイルを殺して動作性能と命中精度を上げちゃえっていう発想。
③COWCOW ボアアップローディングノズルセット
これも作動性向上の肝となるパーツ。シリンダー内径を14mmとすることで、リコイルとキックを上げます。
個人的にはFireflyのロケットバルブより効果を感じました。
【バレル】
④KM企画 TNパーフェクトバレル デトニクス45用
弊ブログでご紹介した数多くの東京マルイ製ブローバックガスガンに施してきた、『Top Gun流』カスタム。
あえて純正より短いインナーバレルを使うことで、マズルまわりをリアルにする手法です。
ここではデトニクス45用を使っていますが、USPコンパクト用でもOK。
初速が若干下がりますが、リアル派にとってはマズルから見えるインナーバレルのほうが激萎えなんです。
(この気持ち分かってくれる人いるかな・・・?)
⑤Firefly うましか辛口
命中精度と飛距離を上げる、独特な形状をした突起を持つパッキン。
個人的に0.25g以上の重量弾が好きなので、赤い辛口(硬め)を選択。
VSR-10にも使っていてある程度効果を実感したので、グロックにも装着した次第です。
【フレーム】
⑥GUARDER カスタムフレーム(USA刻印)
Gen2化するにあたって必須となるアイテム。
アメリカのアクション映画に出ている個体は恐らくGlock USA製であることから、USA刻印を選択しています。
リアル派ガンマニアにとっては忌まわしき(失礼!)『MADE IN JAPAN ASGK TOKYO MARUI』を取っ払い、
『MADE IN AUSTRIA GLOCK INC.』のリアル刻印にできちゃう浪漫あふれるパーツです。
⑦GUARDER シリーズナンバータグセット(上記フレームに付属)
東京マルイのグロックシリーズは、ご存知の通りシリアルナンバー部がマニュアルセーフティになっています。
過去にノーマルで使っていた時、これが勝手にかかってしまい肝心な時に撃てないというトラブルがありました(実戦なら命取り)。
それを嫌った結果採用したパーツです。実銃のようにリアルにできるので一石二鳥。
ただ、頭3桁のアルファベットがなぜか『GAR』になっていて残念ポイントといったところ(東京マルイは『DMD』)。
尚、組付については過去の記事に載せていますのでご参考までに。
⑧GUARDER スタンダードスチールスライドストップ
本体の強度だけでなく、塗膜と質感もマルイ純正から向上させるべく装備しました。
⑨GUARDER スチールスライドロック
これも塗膜強度と質感の向上を狙って取り付けたパーツ。
【マガジン】
⑩GUARDER アルミマガジンケース
純正の重い亜鉛合金から解放される、軽量化カスタムのカギとなるパーツです。
刻印や残弾確認孔のモールドもなかなかリアルで◎。
塗膜もかなり強いので、多少抜き差ししたくらいでは剥がれません。
⑪GUARDER アルミ強化マガジンベースマウント
これもマガジンの軽量化を目的としたパーツ。
アルミマガジンケースと別売なのが財布に痛い・・・。
⑫GUARDER マガジンバンパー
ガス注入口を隠し、リアルにできるパーツです。
一体今までグロック17一丁だけにいくらかけてきただろう?と改めて感じます。
数多くのパーツを試してみて、気に入ったものだけに厳選したらこうなった、という感じです。
(何気にGUARDER率高いな笑)
お気づきの方もおられるかも知れませんが、このカスタムによってエアーコッキングガン並の軽さになります。
たいていの人がコレを手に取ると、そのあまりの軽さに笑ってしまいます。
リアリティという観点から逆行しますが、そこはあくまで実用重視にしました。
また、スライド自体はノーマルのままにしています。
カイデックスホルスターからのドローをよく練習するので、すぐに先端部が摩耗してしまうんです。
よって、スライドは定期的に純正品に交換するため、消耗品としています。
厳密にはGen2とGen3はエキストラクターの形状が異なるので、スライドはGen3、フレームはGen2というチグハグさがありますが、そこはご愛敬ということで・・・。
これでもトリガーや内部ハンマーなど、まだカスタムの余地を残しています。
摩耗して部品交換が必要になったら、また新しい部品を試してみることにします。
尚、当方のカスタムについては完全に自分好みの自己満足であり、性能UPについてはプロのショップさんには敵いません。もし参考にされる場合はあくまで自己責任にてお願い致します。
今回はここまで。ではまた。
2018年01月21日
東京マルイ Glock17 Gen2化カスタム
マルイグロックの第2世代モデルが欲しい。
そう願ってやまない、オールドグロックファンの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
僕もその一人です。
1990年代のハリウッド映画に登場するグロックと言えば、どれも第2世代モデル。
その時代の映画を見て育った僕には憧れの銃です。
さらに、子供の頃に遊んだエアーコッキングのグロックも、第2世代モデル。
自分にとっては何気に思い入れがあるんです。
しかし、残念ながら東京マルイ製ガスブロのグロック17はレール付きの第3世代モデル。
カスタムパーツもないので、第2世代モデルなんて空想の産物。
そんな風に考えていました。
そう、ついこの前までは。
昨年の夏、そんな夢を現実にしてくれるカスタムパーツが、GUARDERから発売されました。
今回は、GUARDER製東京マルイグロック17用Gen2オリジナルフレームを用いたカスタムの模様をお届けします。
パッケージ。
他のGUARDER製フレーム同様、本体は袋に入っています。
ラインナップは刻印の違いからEUROバージョンとUSバージョンがあります。
僕は個人的な好みからUSバージョンをチョイス。
パーツ本体。
実銃の雰囲気や質感をうまく再現しています。
もちろんリアル刻印。
激萎えポイントであったメーカー刻印とは、これでおさらばできます。
第2世代なのでダストカバーにレールはありません。
現代ではタクティカルな場面で必須なレールですが、オールドファンには要りません(笑)
フィンガーチャンネルのないグリップ。
第1世代ののっぺらぼうなグリップよりは断然手に食いつくので好きです。
付属品はフロントシャーシシャフトとシリアルプレート。
シリアルプレートが標準装備なので、煩わしかったマルイ純正のマニュアルセーフティをオミットできます。
あれたまに勝手にかかったりするので嫌なんですよ(笑)
組み立てる際に気になった点がひとつ。
どうやらフレーム内側とインナーシャーシとの間に空間があるようで、セーフティ板ばねが適正位置で固定されず、テンションを維持できないので、そのまま組むとスライドロック(フレーム中央、トリガー上部のテイクダウンレバーのようなもの)が機能しなくなるトラブルがありました。
そこでフレーム(赤丸の部分)に細工します。
セーフティ板ばねのテンション確保のため、適当な厚さのプラ板を設置。
これできちんとスライドロックが機能するようになりました。
さて、あとは組み立てるだけなのですが、よりリアルな第2世代モデルにするためスライドに一工夫します。
知ってる人は知ってると思いますが、第2世代モデルと第3世代モデルのエキストラクターの形状は異なります。
第2世代モデルが平たいのに対し、第3世代は前部に突起があります。
というワケで、カッターとやすりで突起を削り落としました。
スライドに手を加えたので、塗装します。
前回のM11-A1と同様、
プラスチック用プライマー → インディ・パーカーシール → アクリルラッカー
の順で3層塗装します。
完成。
念願の第2世代グロックがついにできました。
多少調整と工夫が必要な部分もありますが、比較的簡単に仕上げることができました。
第2世代万歳のオールド好きの方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
2017年12月09日
SIG Sauer M11-A1 試作 (東京マルイ P226E2ベースカスタム)

実戦でガンガン使える、SIG P220系コンパクトオートは、僕にとって憧れでした。
東京マルイのP228(エアーコッキング)を手にして以来、SIG Sauerのオートに魅了され、長らく愛機として使ってきました。P228は自分にとって程よいサイズで、その洗練されたデザインが大好きでした。
しかし、満足のいくP220系コンパクトのブローバックガスガンをモデルアップしているメーカーは皆無に等しいのが実情です。
国内で唯一モデルアップしているタナカワークスのものは、ルックスの再現度は100点満点なのですが、初期タイプのマグナブローバックエンジンかつ構造上ガス漏れしやすいマガジンなど、あまり信頼できる代物ではありません。
おまけに比較的高価な上、今となっては絶版で入手困難です。
一方、天下の東京マルイはもはやモデルアップする気すらなし。P226 Railの初期のマガジンは分割式で、P220系コンパクトへ派生するためのデザインではないかと期待したものですが、そのマガジンすら絶版となった今、望みは薄いでしょう。
もはや諦めるしかないのか・・・
そんな時、僕にものづくりの神様が降りてきました。
ないものは、腕があるならつくってしまえ。
こうして、長年の構想をカタチにする時がやってきました。
今回は、東京マルイ製P226E2をベースに、SIG系コンパクトオートを製作した過程を記録させて頂きます。
■構想&機種選定

サバゲーやタクトレなど、実戦で使えることが前提ですので、東京マルイのP226E2をベースに開発しました。
P220系コンパクトといえど、P228やP229など魅力的なモデルが複数あります。
個人的に一番好きなP220系コンパクトはP228なのですが、今回はベースのP226E2(削り出しスライドモデル)に比較的スライドのデザインが近い、M11-A1を選定しました。
M11-A1は近年SIG Sauerが発売した、米軍納入モデルのP228(U.S. M11)の民間モデルで、レールなしのフレームに削り出しスライド装備の最新モデルです。
P226E2のスライドとフレームを切り詰め、エキストラクターの形状を変更すればイケるとの判断です。
■試作
まずはスライドとフレームを作りこんでいきます。
東京マルイのP228をサイズのベンチマークに、切り詰めるサイズを決め、プラスチック用のこぎりで切り落としていきます。
さらに今回は、留学時代にアメリカで買った実銃雑誌に偶然M11-A1の実寸写真が載っていたので併せて活用しました。
最初にスライドを3つにカット。
真ん中の不要部分を取り除き、接着していきます。
接着前に補強材を埋め込みます。
細めの六角レンチを適当な長さにカットし、ライターで熱してから埋め込み、スライドを耐衝撃タイプの瞬間接着剤で接着します。
さらにスライド断裂対策に、側面・上部にホッチキスの針を打ち込みます。
針の長さをスライドの厚さに合わせてニッパーでカットしたら、側面に各7本、上部に5本の計19本をスライドに埋め込み、瞬間接着剤で仮止めします。
その上をエポキシパテで埋め、カッターナイフで粗削りしてから紙やすりで表面を整えます。
大型化したエキストラクターは、缶詰のフタを切り出して作製しました。
スライド右側面のエキストラクター部分を削ってから、瞬間接着剤で接着します。
次にフレーム。
東京マルイのP228を目安にダストカバー先端とマグウェルをカットします。
難関がトリガーガードの延長加工。
P226のレール付きモデルとP220系コンパクトのトリガーガードは、形状・大きさともに異なっているため、加工が必要です。
まずはトリガーガード前部をカット。
ここにも補強材を埋め込んだら・・・
エポキシパテと瞬間接着剤で接着・固定します。
あとはカッターナイフと紙やすりで形を整えます。
そしてダストカバーのノンレール加工。
やすりで粗削りした後、エポキシパテを盛り、不要な部分を削って形を整えます。
ミニリューターを使うとより早く作業を進められます。
この他、グリップ取り付けに必要なねじ受け皿を移設したり、ダストカバー内側をエポキシパテで埋めたりといくつかの加工を経た後、全体をやすり掛けします。
やすり掛けは表面を綺麗にするためには最も重要な工程で、納得がいくまで丁寧に根気よく続けます。
このやすり掛けを怠ると、塗装後の仕上がりが悪くなります。
最初に金属やすりやミニリューターで粗削りした後、300番→600番→800番→1000番→2000番・・・と、目を細かくしながらやすり掛けしていきます。
やすり掛けが終わり、形が整ったら塗装していきます。
今回は耐久性を重視し、3層の塗膜で仕上げます。
左から、下塗り(アサヒペン プラスチック用プライマー)→本塗装(インディ パーカーシール)→上塗り(カンペハピオ シリコンラッカースプレー)の順に塗装していきます。
それぞれ24時間の完全乾燥後、順に吹き付けて塗装しました。
塗装のコツは、焦らないこと。
塗りたいものから30cm以上離して、一気に塗らずに少しずつ、シュッシュと吹き付けていきます。
塗装の際はクサいので、十分換気しながら進めましょう。
スライドとフレームが仕上がったら、その他部品を加工していきます。
アウターバレルはカット後、スライド、フレーム同様にやすり掛けして塗装。
リコイルスプリングガイドは金属用のこぎりでカット後やすり掛けし、キャロムショットのガンブルーペンで黒染め。
ショート化に合わせ、リコイルスプリングも2~3巻き程度カットしています。
インナーシャーシは、そのままでは短くなったスライドに干渉して、ホールドオープンに必要なスライド後退量が確保できなくなります。
そこで金属用やすりを使い、ゴリゴリ削ってできるだけ短縮化していきます。
インナーシャーシを極限まで削っても、やはり実銃同様のスライド後退量が確保できませんでした。
このためスライドストップレバーが上がらず、ホールドオープンできません。
そこでスライドストップレバーに一工夫。
写真のように、スライドとかかる部分をミニリューターのダイヤモンド砥石で削り、後退できなかった分の長さを稼ぎます。
同時に、スライドストップノッチもやや広げました。
すべてのパーツの加工が終わったら、組み立てていきます。
グリップはとりあえず手元にあった、東京マルイのP228のグリップを加工して取り付けました。
本音を言えば実銃の純正グリップを取り付けたかったのですが、そんなものが日本で簡単に手に入るワケもなく断念・・・
(ヤフオクとかにたまに出回っているみたいですがなんだか胡散臭かったのでスルー)
フレームが短くなった分、P226のマガジンでは長くてはみ出てしまいます。
しかし、東京マルイのP226エンジンに対応する、P228のマガジンなんてあるはずない・・・
と思いきや、とあるお店にWEのP228用マガジンが転がっていたので即購入。
WEのP226・P228は、東京マルイと互換があるようです。
フルメタルのため本体はまず日本で出回らないはずのWE製P228の、なぜかスペアマガジンだけがあるという謎。
僕みたいな特殊なケースでしか需要がないはずなんですが・・・ともかく助かりました。
他にも、P226の旧マガジンをP228のマガジンにコンバージョンするキットとかも、PRIMEから出ているようです。
ともあれ、試行錯誤の末理想のP220系コンパクトが完成しました。
長年練ってきた構想が、ようやく形になりました。
感無量とは、まさにこのこと。
実射テストも問題なし・・・どころか、P226E2譲りの鋭いリコイルショックに思わずニンマリしてしまいました。
これはイイ・・・!!
命中精度については、やや右に着弾するものの、10mでも良好。
うましか辛口を入れていますが、もう少し調整が必要かも。
初速については、インナーバレルがデトニクス用で短いので50m/s台と低め。
まぁこれでロングレンジを狙うわけではないので良しとしましょう。
スライドトップのSIGマークはオミット。
アイアンサイトはDYTACのルミナスナイトサイト。
実銃のSIGLITEナイトサイトには及びませんが、ローライトコンディションでの戦闘にもある程度対応します。
別パーツのエキストラクターも、思ったよりいい出来です。
撃ち尽くした後のホールドオープンもバッチリ。
■今後の課題
無事に試作機が仕上がったとは言え、まだまだ満足のいくものではありません。
スライド・フレームともに、僕には刻印を入れる技術がなく、今回は断念しました。
一応針とリューターで挑戦しましたが、字が歪みとても綺麗とは言えない仕上がりに・・・
いつも驚くほどに綺麗に打刻されるミリブロガンスミスの皆様には、本当に脱帽です。
また、リコイルスプリングガイドの穴も、手持ちの道具では再現できず断念。
スライドの補強材埋め込み後のやすり掛けも甘く、デコボコしてしましました。
インナーシャーシの長さの関係でスライド後退量が甘く、結果スライドストップノッチをやや広げて対応せざるを得ませんでした。
実用上まったく問題はありませんが、リアリティという点ではイマイチといったところ。
まだまだ課題は多いですが、今回の試作は、まさにこれらの技術的課題を洗い出す「研究用」の意味合いもあります。
その点では、自分ができる技のレンジを探れたので非常に有意義だったと思います。
ともあれ、やっと実戦で使えるP220系コンパクトをカタチにすることができました。
次は今回の経験と反省を踏まえ、さらにクオリティーの高いものを作ってみたいと思います。
ではまた。
2017年02月22日
東京マルイ Glock26(カスタム:近代化改修)

僕はGlock26が大好きです。
どのくらい好きかって?
ガンプロのトシさんの企画「この銃に会いたかった」に記事を投稿しちゃったくらい好きです。
※当時大学生
初めて東京マルイのGlock26を知ったとき。
そして初めて手にしたとき。
あの感動は今でも忘れられません。
そんな思い入れのある愛銃も買ってからずいぶん経ちました。
使い込んだだけあって、さすがにガタがき始めました。

ガワはスティップリングをやったりもしてボロ隠しをしちゃってますが、ついに中身がアウト。トリガーを引いても正常に作動しなくなりました。

スライドストップノッチは長年の使用ですり減り、カッターで切って応急処置を続けた結果、傷口が広がる始末。
お気に入りの愛銃を再び使えるようにしたい。
気が付けば社会人数年目、多少軍事予算に余裕も出てきた今、念願の企画をついにやっちゃいます。
今回は、「Glock26(カスタム:近代化改修)」と題し、オーバーホール兼大規模カスタムの模様をお届けします。
この企画は、ただ同じように修理するわけではありません。
大幅な性能アップと信頼性向上、これが最大の目的です。
この小さな老兵で最新鋭のモデルに張り合うにはどうすればいいか・・・
叩き出した答えは、ある銃を生贄に捧げることでした。
そう、東京マルイ Glock18C。
フルオートガスハンドガンの第2弾です。
新型エンジンによるセミオートでのキレに定評があるこのモデルのエンジンとハンマー回りを移植すれば、同じぐらいよく動くようになるはず。
単純な発想ですが、下手なカスタムパーツを使うより、はるかに実現しやすいやり方だと考えました。
まずはフレーム。
あらかじめ入手しておいたガーダーのリアルフレームに、26のフロントシャーシ、18Cのトリガーまわりとハンマーまわりを移植します。
ここまでは問題なく移植完了し、順調に進みました。
この時までは・・・ね。
次に18Cのエンジン(ピストンASSY)を26のスライドに移植する工程ですが・・・
恐れていた事態がやはり起きました。
ポン付けできない!!
ここで26(厳密には17用)と18Cのエンジンの比較。
左が18C用。
なんと18Cの方が幅も高さも大きいのです。
入らないワケですわ。
しかしここまで来て諦めるワケにはいきません。
中古とはいえ、入手した18Cが無駄になります。
ついに作戦変更。近所のホームセンターでミニルーターを入手。
スライド内側をゴリゴリ削っていきます。
ちょうどピストンASSYが入るくらいの溝を彫ります。
彫り過ぎてスライドに穴を開けないよう、慎重に微調整していきます。
その後順調に彫り進め、無事に18CのピストンASSYをはめることができました。
さて、お次はすり減ったスライドストップノッチの補修。
一般家庭のゴミ箱に眠っているであろう、鯖の缶詰のふたをメディックシザースで写真のように切り出します。
これでノッチ摩耗対策とします。
それをすり減ったノッチの端に瞬間接着剤(耐衝撃タイプ)で接着したら、、、
先程のスライド掘削で出た粉と瞬間接着剤をノッチ上で混ぜ混ぜして即席ポリパテを作ります。
接着剤の上に粉をふりかけ、またその上から接着剤をのせ・・・を数回繰り返し、乾燥させます。
十分に乾燥させたら、実銃写真を参考にカッターナイフと紙やすりで形を整えます。
ここでいったん仮組み。
すり合わせも問題なし。
ただし、試射してみるとフルオートオンリーに(笑)
原因はエンジン後端部のセレクターパーツを取り外したため。
セミオート縛りにするには、このパーツをセミオート位置で固定する必要があります。
そのためにもう一工夫します。
再び鯖缶のふたに登場してもらいましょう。
今度は写真のように切り出したら・・・
図の位置に設置しセレクターパーツをセミ位置で固定します。
そして上からセレクターストッパーを元通りに組むだけ。
これでセミオート縛りにできます。
そしていよいよスライドの塗装。
実銃はほんのりブルーのかかった艶消し仕上げですので、少しでも質感を近づけるべく、キャロムのブルースチールを購入。
十分に換気できる部屋で、よく振ってから、20cm以上離して少しずつスプレーをふいていきます。
焦っていっきにスプレーするとムラができるので、シュッシュッと少しずつがコツ。
塗装が終わったら、一日以上放置して塗料を十分硬化させます。
その後シリコンをつけた布で磨いてやるとツヤがでます。
最後に組み立て。
リアサイトはエンジンの高さの関係上、18Cのものを使用する点に注意。
ついに完成しました。
長年連れ添った相棒が、見違えるくらい生まれ変わりました。
実射性能は驚きの一言。
中身が18Cなので、リコイルもはるかに俊敏で凶暴になりました。
タップ撃ちしても指にしっかりついてきます。これはスゴい。
苦労して組んだ甲斐がありました。
生まれ変わった相棒を改めて手に取ると、あぁこれだ、これが求めていた理想のGlock26だと心底思いました。
かつて憧れた「最小にして最強の」サブコンパクトに、改めて惚れ直しました。
これからも一層大事にしていこうと思います。
ホップパッキンもいいのに交換しようかな。
※このカスタムを参考にされる場合は、すべて自己責任にて行って頂きますようお願い申し上げます。また、調整・空撃ち等の試射を含め、作動させる際は必ずアイウェアを着用してください。









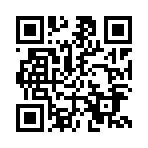
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fa67.c9590ec3.1da9fa68.f1a4735d/?me_id=1267315&item_id=10001933&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmilitary-base%2Fcabinet%2Fa%2Fgd-2%2Fglock-73white.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fb69.f3d782a9.1da9fb6a.76c776c8/?me_id=1335776&item_id=10004273&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fairgunmarket%2Fcabinet%2Fimage%2Fitem_newrobo02%2Fimgrc0088378710v.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fbba.503c434b.1da9fbbb.3fc9c8d1/?me_id=1283624&item_id=10006012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsidearms%2Fcabinet%2F03092590%2F04865831%2Fimgrc0072341683.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1daa0133.01783576.1daa0134.ac7dbef9/?me_id=1356002&item_id=10018451&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faudilarmz%2Fcabinet%2Fimages03%2F4580465980629.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fa67.c9590ec3.1da9fa68.f1a4735d/?me_id=1267315&item_id=10006805&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmilitary-base%2Fcabinet%2Fa%2Fitem14%2Fff-gb-003.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fa67.c9590ec3.1da9fa68.f1a4735d/?me_id=1267315&item_id=10008353&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmilitary-base%2Fcabinet%2Fa%2Fitem17%2Fglk-199bk.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fa67.c9590ec3.1da9fa68.f1a4735d/?me_id=1267315&item_id=10001430&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmilitary-base%2Fcabinet%2Fa%2Fgd%2Fglock-44abk.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fa67.c9590ec3.1da9fa68.f1a4735d/?me_id=1267315&item_id=10002065&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmilitary-base%2Fcabinet%2Fa%2Fgd-2%2Fglock-72bk.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fa67.c9590ec3.1da9fa68.f1a4735d/?me_id=1267315&item_id=10011758&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmilitary-base%2Fcabinet%2Fa%2Fitem24%2Fglk-150abk.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9fa67.c9590ec3.1da9fa68.f1a4735d/?me_id=1267315&item_id=10010508&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmilitary-base%2Fcabinet%2Fa%2Fitem21%2Fglk-151.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da9ff8a.5c767dbc.1da9ff8b.5df3a8c2/?me_id=1347627&item_id=11093439&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Funion5255%2Fcabinet%2Fimgsrc0%2Fd1094%2Fd10941%2Fb00o5v897q.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)